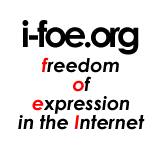甲22号証:陳述書(2)(2006/10/21)
甲22号証(原告:松井氏提出書類)
本件訴訟は2007年3月に第一審判決が言い渡され、既に確定しています。このページは、ネット上の表現を巡る紛争の記録として、そのままの形で残しているものです。
文字化けを防ぐため、ー記号の置き換えなどを行っています。
甲第22号証
陳述書(2)
2006年10月21日
横浜地方裁判所 第9民事部 御中
住所 *****************
氏名 松井 三郎
既に提出済みの私の陳述書(甲9)についての補足説明、及び被告の陳述書(乙11)に対する反論は以下のとおりです。
1私の研究経歴等
私の経歴等は既に提出済みの陳述書(甲9)で述べたとおりですが、私の研究者としての基本的な姿勢を理解していただくために、少し補足説明をさせていただきます。
(1)私が研究者を志した動機
私が京都大学の学部学生時代に、水俣病の原因論に関して大きな論争がありました。当時、熊本大学医学部は「有機水銀説」を公表しましたが、これに対して東工大の故清浦雷作教授や通産省(当時)が強く異を唱えていました。私は、自分の眼で真偽を確かめたくて、熊本大の入鹿山教授を訪ね、「有機水銀説」に至った経緯について詳しいお話をうかがいました。その結果、私としては、清浦教授や通産省の主張はおかしいと思いましたが、他方、環境汚染問題は大変複雑なので、その解明のためには科学的知見の発展が極めて重要であることを痛感しました。そして、そうした科学的知見の発展のために、自分も尽力してみたいと思うようになりました.
当時は大学紛争の最中でしたが、私は、日本の将来を考えると、大学紛争よりも公害問題の解決がもっと重要になると思い、テキサス大学大学院留学を決意しました。私の関心は、環境中の有害物質(例えば有機水銀)がどのようにしてヒトや生態系に影響を及ぼし、どのようにして再び環境に排出されるかを解明することにありました。これは、その後、現在に至るまで、ずっと一貫して私の研究の中心的課題に据えてきている基本テーマです。
テキサス大学では、塩化水銀やメチル水銀が植物プランクトンに取り込まれる機構と排出される機構について研究し、これにより博士号を取得しました。
この成果は、重金属汚染を浄化するために植物を利用する技術開発の参考になりました.また、私がテキサス大学在学中に、ワトソンとクリックが書いたDNAの二重らせん構造に関する論文が全米で大きな関心を呼んでいました。私も大きな関心を持ちました。そして、化学物質の汚染というのは、DNAとの化学反応を起こすことがその本質なのではないかと考えるようになりました。
(2)茨城県土木部技師時代(1972〜1975)
アメリカから帰国後、私は茨城県土木部の技師として、鹿島臨海工業地帯にある鹿島下水道事務所で勤務することになりました。鹿島の石油コンビナート(当時は約20社)からの工場排水を集中して処理する県営の新設の下水処理場(深芝処理場)の一部設計及び運転管理、技術教育等が主要な仕事でした。コンビナートからは極めて多種類の人工化学物質が排出されてきておりましたので、これを全て県営の下水処理場で処理することは不可能でした,そこで、私は、下水処理場での処理の基本である「活性汚泥微生物による分解作用」を用いた処理が可能かどうか(活性汚泥分解性)を処理場の受け入れ基準とし、各工場は責任をもって、分解し易いように前処理するなどしてこの基準を満たすようにするとともに、分解できない化学物質については排水しないこととする旨の行政指導基準を確立しました。いわゆる工場排水処理について生産者責任の原則を徹底した訳です。
この頃(確か1973年11月頃と思います)、被告がこの深芝処理場の立ち入り調査を求めてきたことがありました。被告は、工場排水には有害物質が含まれているので、それを公共下水道に入れるべきではないなどとして、流域下水道に強く反対し、個人下水道(合併処理浄化槽)を提唱していました。しかし、私は、流域下水道か個人下水道かという問題ではなく、工揚排水処理を生産者の責任できちんとさせるという生産者責任を法的に確立する必要があると考え、前述の行政指導基準を確立させていました。そこで、私は、被告の要求を受け入れ、全面公開に応じました。当初は、国・県の役人から懸念の声が出されていましたが、私は、同処理場の運転管理の技術責任者として、法律違反をしていない自信がありましたので、上層部を説得し、同僚や部下の了解を得て、全面公開に応じたのです。24時間にわたって毎時処理場の流入水や処理水から試料を採取し、同一試料を半分にして双方で分析を行いました。被告らのグループには活動場所としてテントを提供し、処理場内の分析室の使用も許諾しました。その結果、どの試料についても法律違反は認められませんでした。
(3)「枯草菌RecーAssay」検出法の開発
1975年に金沢大学の助教授として赴任してからは、排水や水道水に含まれる有害化学物質を検出する方法の開発に着手しました。私は、環境汚染物質の有害性の中心は遺伝子の損傷にあると考えておりましたので、金沢大学医学部癌研究所や国立遺伝学研究所の指導・協力により、DNAに損傷を与え突然変異を引き起こす物質の研究を行い、その結果、「枯草菌RecーAssay」検出法の開発に成功しました.
当時は、カリフォルニア大学のエイムス教授がサルモネラ菌を利用した突然変異検出法(エイムズ法)を提案され、世界的に利用が開始された頃でした。しかし、水道処理水など含有物質が少ない場合にはエイムズ法も有効でしたが、下水や工場排水の場合には、これらに含まれる毒性物質によってサルモネラ菌が死滅してしまうので使えませんでした。「枯草菌RecーAssay」法は、このような下水や工場排水についても突然変異性のみならず遺伝子損傷性をチェックすることができるうえ、エイムズ法では検出評価できない水銀、クロム、カドミウム、鉛、砒素などの重金属類の遺伝子損傷性も検出できる画期的な方法でした。
1986年に京都大学助教授となり、翌1987年に同大学工学部附属環境微量汚染制御実験施設(大津市)の教授に昇格しました。ここで、私は、「枯草菌RecーAssay」法を活用して、琵琶湖・淀川水系の汚染状況や下水処理場・し尿処理場の調査、水道水浄化処理の調査を行い、遺伝子損傷の状況把握を行いました。これは、後に大阪市が淀川原水の悪臭・汚染に対処するために全国で初めて高度浄水処理を導入する契機のひとつとなりました。
1995年、こうした「枯草菌RecーAssay」法や琵琶湖の富栄養化防止研究、世界湖沼の水質保全活動が認められ、カナダ環境省淡水研究センターから「ヴォーレンワイダー博士記念賞」を受賞しました。
(4)環境ホルモン研究
この記念賞の受賞講演のためカナダに渡航したところ、環境ホルモン問題を提起した『Our Stolen Future』(邦名『奪われし未来』)という本(英語版)を贈られました。帰国途中に読んだところ、私が以前から抱いていた疑問点に対する解答が書かれていたのです。すなわち、「遣伝子損傷」という視点で水環境中の野生生物への影響を観察してみると、遣伝子損傷性物質の水環境汚染のレベルが低いにもかかわらず、野生生物に奇形などの異常が発生しているのです。私は、なぜこのような現象が発生しているのか、その原因がよくわからず、もしかしたら、遣伝子損傷以外にも、ヒトや生態系に悪影響を引き起こすメカニズムが働いているのかも知れないと思っていました。『奪われし未来』は、まさにその別のメカニズム(内分泌かく乱作用)について問題提起していたのでした。私は、この本を読んで、有害な環境汚染物質が、ホルモン受容体との結合を介して、遺伝子を動かし、その結果、奇形などの異常が発生しているのに違いないと確信しました。
そこで、私は、早速、イギリスのサンプター教授からヒト女性ホルモン受容体を組み込んだ酵母を入手し、研究を始めました,また、アメリカのミューラー教授からもヒトのダイオキシン受容体を組み込んだ酵母を入手し、ダイオキシン類やベンゾ(a)ピレンなどの多環芳香族類の内分泌かく乱作用の研究を行ってきました。こうした研究の中で、私は、内分泌かく乱作用の解明には多分野にわたる学際的な取り組みが不可欠であると考え、1年間をかけて多分野の研究者の方々と研究計画を練り上げました。そして、2001年度から、文部科学省科学研究費補助金特定領域研究「内分泌かく乱物質の環境リスク」班を立ち上げ、その代表となりました。被告がこの研究の主査を担当していたのは既述のとおりですが、私の方から依頼した訳ではなく、文部科学省から指定されていました。
この研究は2003年度まで継続し、文部科学省の最終評価もAクラスと高い評価を得ました。約300名の研究者が参加し、従来あった学者間の壁——医学、生物学、遺伝学、薬学、農学、工学の縦割り的研究組織の壁——を完全に乗り越え、遺伝子マイクロアレイを大幅に導入した研究手法の開拓に加え、毒性評価の指標(エンドポイント)を、生殖系のみならず、脳神経系や免疫系への影響とその関連性、さらには環境ホルモン物質の代謝過程での突然変異物質との関連性にまで広げることができました、そして、この3年間で、参加した大学において約100名の博士号取得者を誕生させることができたのです。
(5)変異原性物質の作用メカニズムの究明
「枯草菌RecーAssay」法による汚染調査が水道水の高度浄水処理導入の契機となったことは既述のとおりです,ところが、その後、水道水の塩素処理によってトリハロメタン等の有機塩素化合物が副生成され、これらが発癌性物質であることが指摘されました。これを機に、水の塩素処理によって発生する副生成物に関する研究が進むようになりました。
私は、1996年〜1998年、アメリカNSF一日本学術振興会共同プログラムに応募し、認められイリノイ大学との共同研究を行い、水道水の塩素処理やオゾン処理によって副生成する多くの有機ハロゲン物質の中で最強の問題物質が塩素ー2臭素酢酸であることを突き止め、国際水質学会で発表しました。
また、当時、トリハロメタン類を生成する塩素処理に代えてオゾン処理に変更しようという意見が大勢を占めていましたが、私は、オゾン処理によっても、アルデヒド類、アクロレイン、臭素酸などの遺伝子損傷性物質、変異原性物質が生成されることを国際誌に発表し、そのような安易な技術転換は拙速で、慎重に検討を要すると問題提起しました。
さらに、私の関心は、このような変異原性物質の作用メカニズム——つまり、これらの物質がどのようにして変異原としての機能を発揮するのか——の究明に向かいました。1996年に、当時最も進んだ分析機器を購入し、DNA付加体の分析方法の開発に着手しました。DNA付加体とは、DNAの塩基にさまざまな化学物質の分子が結合したもので、最新の研究で発ガン性などの毒性発現を引き起こすもとになるものであることがわかってきました、
前述のとおり、既に環境ホルモンの研究にも着手しておりましたので、並行的に研究を進めることで、2002年に、ヒトの臓器細胞のDNA付加体を網羅的に解析する画期的な方法の開発に成功しました。その結果、臓器によってDNA付加体の種類と損傷の多寡に大きな違いがあることを発見しました。この発見は、ベンゾ(a)ピレンのような肺がん誘発性の高い物質が、どのような種類のDNA付加体を生じさせるかを解明する道筋を開きました。
また、ダイオキシンとベンゾ(a)ピレンは、ともに内分泌かく乱作用がある物質ですが、その解毒機構の違いによって突然変異原性の発現メカニズムに違いが出ることがわかってきました。これが、環境ホルモン物質の毒性メカニズムの解明へのひとつの手がかりとなりました。
2 私の環境ホルモン研究の成果
ここで、私の環境ホルモン研究でわかってきたことを簡単に説明しておきたいと思います。
(1)ダイオキシン類の有害性の研究にあたっては、前述のとおり、私は解毒機構の違いが突然変異性の違いとなっていることを突き止めていましたので、その解毒機構を解明しようと考えました。
解毒とは、簡単に言うと、体内に入った有害な化学物質が体外に排出されることで、酸化・還元反応の結果、抱合体を形成して尿・便・汗などとともに体外に排出されるというメカニズムです,抱合体形成とは、細胞外に出にくい脂溶性の物質を排出しやすい水溶性の物質にするために、硫酸基・グルタシオン基などが結合することをいいます。
解毒機構解明の手始めに、ヒトの尿中のダイオキシン類を測定したところ、尿中からはダイオキシン類は検出されませんでしたが、代わって藍染の染料であるインディゴやインディルビンが尿中に排出されていることを発見しました。
これは、世界で初めての発見でした。
インディゴ、インディルビンは、藍染の染料物質として知られており、中国では古くから漢方薬として用いられています。このような物質が尿中に検出されたということから、一挙に解毒機構の解明が進みました。これまで、食物中のタンパク質に含まれるトリプトファンの2分子が腸内細菌によって結合されて前駆体が作られることはわかっていましたが、さらに私の研究室で調べてみると、肝臓でインディゴ、インディルビンが合成されていることがわかりました。そして、このインディゴ、インディルビンは、AhRという受容体と結合し、酸化・還元・抱合体形成を経て尿に排出されることが判明したのです。AhRは、ダイオキシン受容体と呼ばれ、ダイオキシンや多環芳香族類と結合することがわかっていましたが、その詳しい機能は不明でした。
私は、本来はインディゴ、インディルビンを解毒排除するための受容体であって、それが誤ってダイオキシン類やベンゾ(a)ピレンなどの多環芳香族類と結合してしまっているのではないか、との仮説を立てたのです。
もう少し詳しく説明します。
(2)ダイオキシンも、インディルビンも、ベンゾ(a)ピレンも、細胞内に侵入するとAhRに受け止められて複合体を形成します。それが遺伝子に信号を送り、遺伝子の配列に対応した酵素群を生成させます.一方、信号を送り終えた分子は、AhRから離れ、それ自身に酸化・還元・抱合体形成の解毒反応が進行します。この解毒反応は、物質によって大きく異なっています。
インディルビンは、容易にこのような解毒反応が進行し、最後に尿中に排出されます。インディルビンの毒性はあまり強くはありません。
一方、ダイオキシンは、全く解毒機構が働かず、細胞内に長くとどまって、不必要に解毒機構に関係する遺伝子群を動かします。その結果生成された酵素群は、ダイオキシンに対しては解毒のはじまりである酸化等の化学反応を起こすことができないのに、他の細胞内物質に酸化等の化学反応を仕掛けるのです。
このため、他の物質の解毒(消滅)の動的バランスを失わせ、多面的な毒性効果を生み出してしまうのです。中でも、さまざまな病気を引き起こすとされる活性酸素種を副生することが疑われます。このように、ダイオキシン類のようなグループの化学物質の問題性は、細胞外への排出機構(解毒機構)を持たない点にあります。ただし、わずかずつですが、別の反応によって細胞内から細胞外へ出て、皮脂や便といっしょに体外へ排泄されることはあります。
他方、ベンゾ(a)ピレンは、酸化・還元・抱合体形成の解毒反応は進行するのですが、その一連の過程で、酸化したベンゾ(a)ピレンが直接DNAに結合し、DNA付加体となって突然変異を起こす契機となります。また、酸化・還元が繰り返されてペンゾ(a)ピレンのキノン体(酸素分子が2つ結合したもの)となり、これがDNAと結合してDNA付加体となって、突然変異を起こす契機ともなります。さらに、この酸化・還元を繰り返す過程で活性酸素種が生み出され、これがDNAに結合してDNA酸化付加体(酸素分子が結合したDNA付加体)を形成し、突然変異を起こす契機となります。
活性酸素種は、付近に細胞膜があるとそれにも酸化を仕掛け、細胞膜損傷の毒性を引き起こします。細胞膜を構成する脂質が活性酸素種で酸化されて、アルデヒド類が生成され、これがDNA付加体を形成することを、私どもの研究室で確認しています。また、活性酸素種は、付近に酵素があるとそれを酸化して酵素の機能を阻害して、毒性効果を引き起こします。
このほか、AhRとの結合が弱く遺伝子群を動かさない物質群もあります。タバコの煙や自動車の排ガスの中には、このグループに属する環境汚染物質が多数存在しています。これらの物質も、積極的には酸化・還元・抱合体形成の解毒機構は働かないのですが、AhRとの結合力が弱いので、他の物質により解毒機構が働いた際に副次的に解毒される可能性があります。
(3)こうした研究過程の中で、私は、最近急速に技術開発が進められているナノ粒子問題、とりわけC60ーフラーレン物質のことが気にかかりました。というのは、この物質は、水には溶けにくいのですが、細胞膜の脂質分子にはなじみ、容易に細胞内に侵入することが知られていたからです。ダイオキシンの炭素数は12、ベンゾ(a)ピレンは20に対して、C60ーフラーレンは炭素数が60もあります。当然ですが、これだけ大きな分子が果たしてAhRで受け止められるだろうかという問題があります。もし受け止められないとすると、いったいどのような解毒機構で細胞外に排出されるのかという疑問が生じます。
また、C60ーフラーレンは電子伝達能力(電導性)が優れているのですが、それによって酸化還元反応を起こすことはないのだろうかという懸念も生じます。現時点で、C60ーフラーレンの毒性機構について最も重要視されているのは、細胞内で活性酸素種を発生させ、それが酵素や細胞膜脂質、遺伝子DNAに強い酸化作用を働かせるという仮説です。これは、国立医薬品・食品衛生研究所の山越さんらが提唱しておられる説で、私が本件シンポジウムで示した京都新聞で紹介されているオーバーデルスターの論文中に引用されています。
私は、これまでの私の研究からも、ナノ技術を安易に利用する前に、内分泌かく乱性及び遺伝子損傷性の両面から、その安全性を検討する必要があると考えました。
そこで、私は、「ナノ素材の毒性・代謝機構とその環境影響評価」というテーマで文部科学省の科研費申請を行い、2005年度から交付を受けています。現在も研究中ですが、これまでの研究で、C60ーフラーレンは、山越さんらが提起された活性酸素種の発生だけでなく、DNA付加体を形成させることも確認しています。一方、解毒機構については、AhRはC60ーフラーレンと結合しないことがわかりましたが、他の解毒機構は発見されていません。解毒機構が働かなければ、細胞に長く留まって、さまざまな悪影響を及ぼすことも考えられます。
このように、私は、これまでの環境ホルモン研究の成果から、ダイオキシンなどの環境ホルモンとナノ粒子は毒性メカニズムが共通しているのではないかと考え、ナノ粒子の研究に着手したのですが、その結果、やはり共通性があることがわかりました。こうしたメカニズムは、ナノ粒子を含む化学物質の毒性というものの正体ではないかと私は考えています。
3 私と被告との関係について
被告は、陳述書の中で、私のとの関係で特記すべき事項として、1)境川流域下水道、2)NEDO主催ワークショップ(2004年12月14日)、3)科研費主査を挙げています。これ以前にも、前述のとおり、私が茨城県土木課技師として深芝下水処理揚に勤務していた時に、被告から立ち入り調査を求められ、私がこれに応じて全面公開したことがありました。
1)の事件について、少し補足説明させていただきますと、被告が記載している裁判において、被告は訴訟の原告(地主)側の証人として、私は訴訟の被告であった愛知県及び建設省側の証人として、それぞれ証言をしました。前述のとおり、被告は、流域下水道に強く反対していました。一方、私は、流域下水道に賛成か反対かというのではなく、排水や水質についての法的規制を強化し、生産者の責任で、公共下水道に放流する前に工場排水の適切な処理を実行させるべきであると考えています。その考え方に基づき、茨城県の深芝処理場の運転管理をしてきた立場から、境川流城下水道についても運転管理が可能である旨証言しました。この裁判は、原告(地主)側が敗訴しました。
4 「環境ホルモン問題」をめぐる意見の対立について
(1)環境ホルモン問題は、人工の化学物質が人間を含む生物のホルモン作用をかく乱することによって、人の健康や生態系に看過できない影響を与えているのではないかということが懸念されている問題です。内分泌系などのホルモンの働きをかく乱するという新たな毒性概念が発見されたこと、しかも、従来の発ガン作用量などよりもずっと低用量で作用することが注目され、社会的に大きな関心を呼びました。当初は、「メス化」などの生殖系への影響がクローズアップされていましたが、その後研究が進むうちに、免疫系や脳神経系にも影響を及ぼしている可能性があることがわかってきました。
この問題をめぐる事実経過は、別表のとおりです。当初は、アメリカで大きな問題となり、取組みが始められましたが、クリントン大統領からブッシュ大統領へと交代したことからアメリカでの取組みは足踏み状態となり、その後は、むしろ日本が、毎年国際シンポジウムを開催するなど、この問題についてリーダーシップを発揮するようになりました。
環境ホルモン物質の代表格であるダイオキシンについては、日本の対策が遅れていたこともあって、1999年2月、所沢産の野菜のダイオキシン汚染がテレビ報道されたことがきっかけとなって、国民の不安が一挙に噴出しました。
これを機に、政府内でもダイオキシン対策が強化され、同年6月には「ダイオキシン類対策特別措置法」が議員立法で成立しました。
このような状況の中で、文部科学省でも環境ホルモン研究が推進され、2001年度(平成13年)から2003年度(平成15年)まで私が代表者をつとめる特定領域研究「内分泌撹乱物質の環境リスク」が行われ、研究成果をあげたことは既述のとおりです。
(2)しかしながら、この問題については、産業界を中心に、「心配するほどの問題ではない。騒ぎすぎだ。」という趣旨の意見が出されていました。被告は、そうした意見を代表する学者の一人です。1998年12月には、被告は『新潮45(12月号)』に、「環境ホルモンから騒ぎ」と題する文章を掲載しています。
その後、1999年に林俊郎氏が『ダイオキシン情報の虚構』(健友館)という本を出版され、さらに2003年には、渡辺正氏と林俊郎氏の共著で『ダイオキシン 神話の終焉』(日本評論社)が出版されました。この頃から、新聞・雑誌などでも「ダイオキシン・環境ホルモンは大した問題ではない。空騒ぎだったのだ」というような論調の記事が散見されるようになりました。
さらに、この頃から、これまでこの問題の牽引役でもあった環境省自身にも、変化が見られるようになりました。2003年10月、環境省は、1998年5月に策定した「環境ホルモン戦略計画SPEED’98」の改定作業に着手しました。その結果、2005年3月に新たに「ExTEND2005」が策定されたのですが、その内容は、とりわけ環境ホルモン問題の重大性の認識において、従来の「SPEED’98」から後退するものになっています。
(3)このような意見対立の背景には、「環境ホルモンのリスク」についての考え方の違いがあります。被告は盛んに、環境リスクについては、定量的評価を行い、リスクの程度や他のリスクとの比較を議論しなければならないと主張しています。私も、これを否定するものではありません。しかし、環境ホルモンの場合、問題は、化学物質の環境汚染リスクを定量的に評価する基礎となる統計情報が限られている点にあります。ヒト集団の死亡率統計については日本政府の定まった統計方法があり、全国の保健所を通じてまとめられ、癌死亡統計まで整備されています。しかし、死亡以外の有害影響、すなわち環境ホルモンが提起するような、生殖障害(子供を生む能力への影響など)や、神経能活動影響(PCB汚染につき、子供の集団でIQ値に有意な悪影響があった事例など)、性同一性障害などについては国の疾病調査がないため統計値が乏しく、定量的評価は極めて困難な状況にあります。したがって、環境ホルモンのリスクコミュニケーションといっても、定量的な資料の提供ができていない状態なのです。ここに環境ホルモン問題の難しさが存在します。
化学物質の有害影響をヒトの集団の癌死亡に注目し寿命の長さに換算する方法は、被告の提案ですが、これは化学物質の有害性を評価する一つの方法にすぎず、それで全てが評価できるものではありません。例えば、人の死亡リスクと、子どもを産めなくなるリスクとをどのように評価して、リスクの大きさで比較するというのでしょうか。死のリスクの方が大きいから、生殖障害のリスクは無視してよいとでもいうのでしょうか。そんなことは許されないと思います。当然のことですが、生殖障害のリスクについても、それをできるだけ削減するために、原因の究明と対策の実施が求められていると思います。
残念ながら、環境ホルモンのリスクについては、未だ原因やメカニズムの究明が十分になされていないのが現状です。むしろ、私がシンポジウムで引用した環境省の上家氏の発言のように、「わからないことが沢山あることがわかった」という状況といっても過言ではないと思います。それでも、私の研究成果でも言及したとおり、研究の過程で人体の解毒機構の解明にもつながる発見があり、この分野の研究を進めることによって、ヒトや生物の毒性学の基本問題の解明が一挙に進展することも期待されます。
私を含めて環境ホルモンの研究者の大半は、環境ホルモン問題の難しさと同時に人体の恒常性(ホメオスタシス)の解明にもつながるという問題の重要性を認識しており、未だ科学的知見が十分でない現段階で、リスク評価を行って「大した問題ではない」と切り捨てるべきではなく、さらに精力的に研究調査を進め、科学的知見の充実に努めるべきであると考えています。
ところが、被告は、自ら提案する定量的なリスク評価方法を強引に環境ホルモン問題にも適用して、「環境ホルモンのリスクは大したものではなく、騒ぎすぎだ」と主張しているのです。当然ですが、産業界も、被告のこの考え方を強く支持しています。被告は、自分でも認めているとおり、環境ホルモン研究の専門家ではありません。ですから、この問題の本質とその重要性をよく理解できていなかったのかもしれません。
また、被告は、陳述書において、旧環境庁が策定した「SPEED’98」に含まれていた67物質(その後65物質)について、環境省が試験をした結果、いずれも「ヒト推定暴露量で影響が見られなかった」としてリストを廃止したことから、当初の報道や専門家の発言が間違いであったと判断しています(8頁〜9頁)。しかし、環境省が実施した試験はリストの65物質中の1部で、全部ではありません。しかも、試験といっても、主として生殖系への影響を評価するもので、脳神経系や免疫系への影響を評価するものではありません。そもそも、内分泌かく乱作用というのは、ごく微量で作用し、メカニズムも複雑なため、その影響を評価する試験方法を確立することは容易なことではありません。国際的にも、未だ内分泌かく乱作用についての確立された試験方法はないという状況で、環境省が実施した試験方法も、日本独自の試行的なものにすぎません。それで影響が見られなかったからといって、「環境ホルモン問題は空騒ぎだった」と結論づけるのは、余りにも軽率と言わざるを得ません。
私は、これまでの環境ホルモン研究を通して、しばしば生命のしくみの複雑さ、精妙さに感嘆し、生命の尊厳というものをますます強く認識するようになりました。いま、生命の安全性にかかわる研究者に求められているのは、生命のしくみの精妙さに比べて人間の知識がいかに貧弱であるかを自覚し、常に謙虚な姿勢で科学的究明に努めるということではないかと思っています。1つの試験方法で影響が見られなかったからヒトヘのリスクは小さいと断定する被告のような態度は、ある意味で生命を冒涜する傲慢な態度で、生命の安全性にかかわる研究者として、厳に慎まなければならないものであると私は考えています。
5 第7回国際シンポジウム開催時の状況
第7回内分泌撹乱化学物質問題国際シンポジウムは、前述のように環境省の姿勢が変わりつつある最中に開催されました。私は、被告がセッションの座長に指名された経過を被告の陳述書で初めて知りました。セッションの企画は全て被告に任されていたとのことですが、当初の被告の企画案では、パネリストのメンバーの中に、環境ホルモン研究者が一人も含まれていなかったそうです。しかし、共同座長の内山巌雄先生が「環境ホルモン研究者ぬきで『環境ホルモンのリスク コミュニケーション』を議論するのはいかがなものか」という意見を出され、内山先生からの依頼で、私が環境ホルモン研究者の立場からパネリストとして発言することになりました。
既述のように、私は、環境ホルモン問題は、人間や野生生物にとって決して看過できない極めて重大な問題であるとの認識がますます強くなっていました。しかし、被告は、既述のとおり「環境ホルモン空騒ぎ」という考えの持ち主です、パネリストのメンバーを見ても、例えば日垣氏や山形氏などは、被告に同調するような考え方に立った記事を新聞・雑誌に書いておられました。私は、もしかしたら、被告は、「環境ホルモンは空騒ぎにすぎなかった。これまでのリスクコミュニケーションの方法には誤りがあった」とでもいうようなまとめ方をされるのではないかと大変心配になりました。環境ホルモン問題は、決して「空騒ぎ」と決め付けてよい問題ではありません。そのことは、WHO(世界保健機関〉をはじめ国際的にも確認されていることです。また、これまでの環境ホルモン研究によって、毒性メカニズムの解明につながる貴重な研究成果が上がってきており、ここでこの分野の研究を縮小させるべきではないと私は考えておりました。私だけでなく、私が代表を務めた科研費研究の約300名の研究者をはじめ多くの研究者達も同じ想いであったと思います。そこで、私としては、そのような想いを、最新の研究成果とともに、ぜひとも聴衆の皆さんに伝えなければならないという使命感を抱いてシンポジウムに臨んでいたのです。
6 アブストラクトをめぐる被告とのやりとりと当日の私の発言について
私のアブストラクトについて、被告から甲第4号証の3のようなメールが送られてきたこと、これに対し私から甲第4号証の2のメ一ルを返信したことは既述のとおりです。
私は、被告が要望した6つの論点のうち、「3)内分泌撹乱物質だからこその問題点は何か」と「4」学者として何が大事か、何をすべきか」について発言するつもりでおりましたので、「ご希望に沿う形で準備します」と返答しました。また、実際にもシンポジウムにおいて、私はこの2点について発言しています。ですから、被告がその陳述書で「そのこと(上記のメールのやりとり)が全く活かされていなかったので、呆然として聞いておりました」と記載しているのは、明らかに事実と相違しています。
また、被告は、陳述書で、「1回目の発言の最後に、急にナノ粒子の問題がでてきて」と記載していますが、これも事実と相違していることは当日の私の発言のテープ(乙第5号証の2)からも明らかだと思います。
これらの被告の記載からわかるのは、要するに、被告は、座長でありながら、私の発言については、最後のナノ粒子に言及した部分以外はほとんど聞いていなかったということです,あるいは、私の発言内容がよく理解できなかったのかもしれません.被告は、陳述書の中で、私の発言につき、「延々と自己の内分泌かく乱化学物質についての研究結果を述べました」として、さも当日のシンポジウムの主たる論点に照らして場違いであったかのように記載していますが、私が自らの研究結果を紹介したのは、被告が要望した6つの論点のうちの「3)内分泌撹乱物質だからこその問題点は何か」について、具体例に即して私の考えを述べたものに他なりません。被告が私の発言内容をよく聞いていなかった(あるいは、聞いていても理解できなかった)だけであって、それをあたかも全面的に私に非があるかのように主張するのはいかがなものでしょうか。
被告は、座長なのですから、私が紹介した内分泌撹乱物質の問題点(遺伝子損傷性と解毒機構の欠如)を十分に理解した上で、そのような物質についてのリスクをどう考えるべきか、リスクコミュニケーションはどうあるべきかについて、議論を深めることができるように、問題整理をすべきだったのではないでしょうか。自らの非を棚上げにして、一方的に他者を批判するという被告の態度は、本件名誉毀損行為と全く共通していることがわかります。
7 シンポジウムにおける私の発言について
(1)被告は、私が、「新聞記事のスライドを見せて『つぎはナノです』と言った」、しかもその意味は、「要するに環境ホルモンは終わった、今度はナノ粒子の有害性を問題にしようという意味である」と本件ホームページで記述し、それが事実であったと本件裁判で主張しています.しかし、これは全く事実に反しています。確かに、私が、「次のチャレンジはこのナノ粒子だと思っています」と発言したことは事実です。しかし、それは決して「環境ホルモンは終わった」からではなく、むしろ逆に、環境ホルモン研究でわかってきたことの延長線上にナノ粒子の毒性の問題があると考えられるからです。私が、どのような意味で発言したかは、私のプレゼンテーション全体のメッセージに照らして理解していただくと、少なくとも「環境ホルモンは終わった」から、「次はナノだ」と言っている訳ではないこと位は、専門家はもちろんですが、一般人にも理解できることだと思います。ましてや、被告は、私どもの環境ホルモン研究の主査まで務めておられるのですから、私の発言さえ聞いていただいていれば、そのような誤解をすることなどあり得ないはずです。なお、本セッションは、「一般向けプログラム」ではなく、「専門家向けプログラム」として企画されており、このため、私の説明も専門的になっていることはご容赦願います。
(2)私の発言の要旨は、甲第8号証のとおりです。甲第8号証の上段のスライドは、当日のプレゼンテーションで私が使用したもので、下段の説明は、私がスライドを使用しながら口頭で説明した内容を記憶に基づいて記述したものです。
私自身は、当日の発言内容をテープ録音しておりませんので、必ずしも一語一句記憶していた訳ではありませんが、概ねこのような主旨の説明をしたというものです。乙第5号証の1のカセットテープ及び乙第5号証の2の反訳を読むと、一部録音されていない部分がありますし、多少、私自身の記憶と違っていた部分もありますが、スライドと照らし合わせながら、さらに私のプレゼンテーション全体の趣旨を酌んで理解してもらえるならば、私が、概ね甲第8号証の下段の説明のような発言をしていたことは理解していただけると思います。
さらに、注意していただきたいのは、私は、前半と後半の2回に分けて発言をしていることです。時間的制約があることはわかっていましたので、私は、まず前半部分で、環境ホルモン研究の成果と研究の重要性を指摘し、後半部分で、環境ホルモンのリスクコミュニケーションの難しさやそれについての私の考え方を述べることにしていました。
(3)前半部分の発言は、主として私の研究室で行った研究成果である、インディゴ、インディルビンの発見から、ダイオキシンの毒性メカニズムに関する仮説を紹介しました。甲第8号証のスライド第6図から第12図までがこれに該当します。前述のとおり、本セッションは「専門家向けプログラム」でしたので、私の説明には専門用語が多く用いられており、専門外の方々にはわかりにくいと思いますので、ここで少し補足説明をさせていただきます。
ホルモン物質は、鍵と鍵穴のように、それを受け止める受容体との1対1の関係が存在しています。例えば、男性ホルモンと男性ホルモン受容体、女性ホルモンと女性ホルモン受容体、甲状腺ホルモンと甲状腺ホルモン受容体の関係です。環境ホルモンが問題となるのは、真のホルモンに化学構造が似ていることから、誤って受容体に受け止められて複合体を形成し、信号を送って不必要に遺伝子群を動かしたり、反対に信号を送ることを妨げることがあるからです。
ホルモン受容体に受け止められると、何段階かのプロセスで信号を送って、細胞内の多くの遣伝子を動かします。最も動かされる遺伝子の一つはCYP1A1遺伝子(酸素添加遺伝子)です。この遺伝子が動かされると、CYP1A1の酸素添加酵素が生成されます.
役割を終えたホルモンは、その後信号伝達を起こさないようするため、自分が動かした遺伝子の中から、例えばCYP1A1酸素添加酵素によって、自らが酸化され、その後何段階かのプロセスを経て、最終的には抱合体となって腎臓から尿中に排泄されます。このような巧妙な仕組みで、ホルモンと呼ばれる極微量の信号物質が生成され信号を送り、排泄され生体内環境の動的平衡を保っているのです。
我々の研究室がインディルビン、インディゴを発見するまでは、AhRは、ダイオキシンや多環芳香族物質の受容体であると考えられていました。しかし、私どもの研究室では、この研究から、AhRの真の役割はインディゴ、インディルビンの受容体ではないかとの仮説を提案しています。
一方、ダイオキシン類はCYP1A1遣伝子を動かしてCYP1A1酸索添加酵素を生成するのに、その酵素によって自らが酸化されることがなく、さらに抱合体も生成されず、細胞外に排出されにくいことが判明しました。つまり、ダイオキシン類は、細胞内に長く留まって不必要に多くの遺伝子群を動かし、細胞内の生化学反応の平衡を乱し、生体内の環境恒常性を阻害していると考えられる訳です。そして、このことがダイオキシンの毒性メカニズムの一端であると思われます。
(4)こうした補足説明及び前述の「2 私の環境ホルモン研究の成果」で述べた部分とを前提に、乙第5号証の2の13頁の終わりから15頁半ばにかけての私の発言部分をご理解いただければと思います。繰り返しになりますが、本セッションは専門家向けでしたから、当日の聴衆のほとんどの方々には、私の研究室の研究成果である、ダイオキシンの毒性機構の一端の解明についてご理解いただけたと思います。この研究成果と仮説は日本で初めてのもので、国際的にも注目されています。
ここまでの説明に続き、最後に、甲第8号証の第13図の新聞記事を示しながら、ナノ粒子の問題に言及したのです。現在、ナノ粒子は、多くの種類が作り出されていますが、ここでは、特にフラーレン炭素(炭素約60個で構成されるサッカーボール状の粒子)のナノ粒子を想定して説明しています。このナノ粒子が、容易に細胞内に侵入することはよく知られており、もし、この粒子に対して、AhRが受容体として働かない場合には、ダイオキシンと同様に、細胞がこのナノ粒子を積極的に排除する機構を持たない可能性が生じます。そのことを指摘する意味で、私は、ナノ粒子に言及したのです。つまり、ダイオキシンの毒性メカニズムについての研究成果を、今まさに開発が進められつつあるナノ粒子についても類推適用して、予防的に対策を取る必要があるのではないかということを訴えたかったのです。乙第5号証の2の反訳だけを読むと、言葉足らずのように見えますが、化学物質に関わる研究者であれば、皆、ナノ粒子の特徴は理解していますから、先のダイオキシンの毒性メカニズムの一端の解明についての私の発言を聞けば、私が、決して、環境ホルモンは終わったから次はナノ粒子だと言っている訳ではないことや、新聞記事だけを根拠にナノ粒子の有害性を問題にしている訳ではないこと位は、容易に理解できたはずです。
(5)このような私の発言の趣旨は、後半部分の私の発言もあわせてご理解いただけると、より一層明らかになると思います。後半部分で、私は、事前に被告から提示されていた論点のうち、環境ホルモンのリスクコミュニケーション特有の問題点や掌者として何をすべきかについて、自分の考えを述べました。私は、被告と同じく「環境ホルモン空騒ぎ」という考え方に立っていると思われる日垣氏や山形氏とは立場を異にすることを明らかにした上で、環境ホルモン問題で対象となっているリスクは、従来の有害性=死という捉え方とは質的に異なるもので、それをわかりやすく表現する方法を科学者が未だ開発できていないことが問題であることを指摘しました。その意味でも、環境ホルモン問題は終わった訳ではなく、われわれには宿題が残されているという趣旨の発言をしました。そして、環境ホルモン研究について国際的リーダーシップを発揮することは、過去、水俣病などの数々の公害事件を生み、今もそれがトラウマになっている日本の研究者や化学産業にとっても、起死回生のチャンスとなるのではないかということも指摘しました。
また、学者としてどうすべきかについては、甲第8号証の第16図を示して、リスク判断の誤りには2種類あることを説明しました。すなわち、間違い1型というのは、科学証明では有害と判断したが、後になってそれが誤りで実は無害であったという場合で、間違い2型というのは、科学証明では無害と判断したが、後になってそれが誤りで実は有害であったという場合です。私は、科学者には間違い1型が多く、それについて被告はさかんに批判しているが、間違い2型の場合は致命的な結果が生じかねないので、間違い2型よりも間違い1型の方がよいのではないかと主張しました。つまり、「無害だから心配ない」と主張していたところ実は有害であったという場合には、既に致命的な被害が発生し、対策を講じても手遅れということになる訳で、科学者としては、そうなるよりも、危険であることを事前に報告する方が、たとえ後に間違っていたとしても、まだよいのではないかという意見を述べたのです。
このような発言からも、私が「環境ホルモンは終わった」という趣旨で発言しているはずもないことは、明らかではないでしょうか,
8 本件記事の不当性について
(1)このように、被告の本件記事は、私の発言を正しく紹介したものではなく、むしろ、正反対の内容のものとなっています。また、甲第8号証や乙第5号証に照らしても明らかなように、私の発言の趣旨を全体的、総合的に把握した上で、それを批判するというのならまだしも、全体の中のごく一部の発言だけを、しかも事実に反して取り上げて批判するもので、到底、科学者らしからぬ態度と言わざるを得ません。
その批判の内容たるや、あたかも私が原論文を吟味せずに新聞記事だけを鵜呑みにしたかのような、およそ研究者の基本的資質が疑われるようなものです。
このようなやり方は、あまりにも卑劣であって、科学者の名に値しないと言わざるを得ません。しかも、被告は、その行為について全く反省することなく、現在も、自己のホームページ上で、私や原告代理人に対する名誉毀損行為を重ねているのです.到底許し難いことではないでしょうか。
(2)被告は、「なぜ、その場で批判しなかったのか」という私の問いに対して、「時間が足りなかった、座長が意見を言うより、他のパネリストの発言時間を確保しなければならなかった」などと述べていますが、そのようなことは言い訳にすぎないと思います。もし、被告の言うように、私が「環境ホルモンは終わった。次はナノ粒子の有害性だ」と主張して、その有害性主張の根拠として新聞記事だけを示したのだとしたら、それこそ「研究者が一般の人に発表するときには、危険の大きさ、ほかのリスクとの比較を一緒に発表すべき」という被告の問題提起からすると、まさに批判の対象となるような態度だったのでは ないでしょうか。現に、被告自身も、だからこそ本件ホームページで批判したと主張しているのです。そのような最も中心的な問題について、時間が足りないから、他のパネリストの発言時間を確保しなければならないからといって問題にしないというのでは、そもそも何のためのセッションなのでしょうか。まして被告は座長なのです。自ら設定したセッションのテーマに沿って議論を深めていく責任があるはずです。本セッションの趣旨について最もうまく議論できる題材が提供されたのに、それを取り上げないというのは、座長の責任にもとることではないでしょうか。被告の弁解は、本セッションの冒頭の被告の説 明とも、また本件裁判での被告の主張とも、矛盾があると言わざるを得ません。
(3)被告は、私が環境ホルモンは終わったと発言したと記述しても、研究者が研究の対象を変えることはよくあることなので、私の名誉を毀損するようなことではないと主張していますが、このような認識はとんでもない誤りです。現在、環境ホルモン問題については、「空騒ぎ」であるとする立場と、そうではなく現実の重大な問題であると考える立場とが大きく対立しています。言うまでもなく、私は後者の立場であり、被告は前者の立場の代表的学者です。既述のように、私は、文部科学省の研究の代表者を務めており、この問題の研究を続けている若い研究者を励まして育成する立場にあります。その私が、反対の立場のリーダーである被告から、あたかも反対側に寝返った裏切り者であるかのように伝えられると、その記事を読んで事実と誤解した若手の研究者の信頼を失ってしまうことは必至です。現に、本件記事を読んだ何人かの研究者の方から「先生は環境ホルモン研究を放棄されたのですか?」という質問を受けました。
また、私が現在副会長を務めている環境ホルモン学会でも質問の声が上がりました。私は、私の立場が誤解されていることに、深く傷つきました。
このように直接質問して下さる場合には誤解を解くこともできるのですが、おそらく私が環境ホルモン研究を放棄してナノ粒子の研究へと転向したとの誤解を抱いたままの方も多数おられると思います。研究者の業績というものは、決して一人で上げられるようなものではありません。そんなことは、同じ研究者である被告は十分わかっているはずです。それを百も承知で、私の信用を低下させる本件記事を掲載した被告のやり方は、極めて卑劣であり、許し難いと思います。
(4)被告は、2005年1月20日、被告のホームページにおいて、「謝罪」と題する記事を掲載していますが、そこには、抗議をしたのが私であることも、私への謝罪の意思も明示されていないため、私の社会的評価は依然として低下したままであって、到底、名誉回復の措置が講じられているとはいえません。私の社会的評価を回復するためには、被告のホームページ上に謝罪文を掲載することが是非とも必要です。
また、被告の本件行為によって一旦貶められた私の研究者としての社会的評価は、容易には回復しえないものです。少なくとも、私の研究分野における研究者に対して、被告が本件記事の訂正と謝罪の意を表明することなしには、名誉の回復は叶いません。したがって、被告のホームページのみならず、私が所属し、現在副会長を務める、日本内分泌撹乱化学物質学会のニュースレター上に謝罪広告を掲載していただきたいと思います。
9 被告の反省の欠如
(1)本件記事について、私が抗議のメールを送ったことやその後のやりとり、本件提訴に至る経緯については、前回の陳述書(甲第9号証の11頁〜13頁)でも簡単に申し上げましたが、少し詳しく説明します。
私は、2005年1月17日頃、知人の研究者から、本件記事は事実なのかという問い合わせを受け、初めて被告の本件ホームページの記事を読みました。
するとまったく事実と異なり、間違った事実に基づく誹謗中傷記事であったため、驚いて、1月17日付で被告に抗議のメール(甲第3号証)を送りました。
すると、翌1月18日朝、被告から「今日はゆっくり読む時間がないので、後日ゆっくり読んでお返事します。」という失礼なメールが来ました(甲第5号証の1)。その日の夜になって「件のホームページを削除しました。後日、おちついてから、もう一度お返事します。ご迷惑をおかけしました。」という返答があったきり(甲第6号証)、その後、被告からはなんの連絡もありませんでした。
同年3月13日になって、被告から、「お返事を申し上げようと思いつつ、年度末の予算やら組織編成に追われ、のびのびになっております。お約束は年度内ということで、今日になってようよう調べ始めたところです。」というメールが来ました(甲第7号証の3)。年度内に返事をもらうなどという約束をしたことはありません。被告が勝手にホームページ上に「どんなに遅くなっても、年度内には結論を出します。」(甲第2号証)と書いたことをもって、「お約束」と称しておられるようです。
また、被告の同じメールに、「私が示した新聞記事を探したが見つからないので、コピーを送ってくれないか」という趣旨の、極めて厚かましい申し入れがありました(甲第7号証の3)。新聞記事については、1月17日付メールで京都新聞の2004年8月28日夕刊トップ記事である旨を既に回答していましたので(甲第3号証)、今頃になって記事のコピーを送れなどというのは失礼な話で、このことからも、被告に真摯な反省の気持ちなどないことがわかりました。そこで、私は、3月15日に「大変不愉快な思いをしております。名誉毀損で提訴する準備をしています」と返答しました(甲第7号証の2)。すると、同日、被告から、「名誉毀損ですか?できればやめて頂きたいです。」という返答はありましたが(甲第7号証の1)、相変わらず、私の名誉回復や私への慰謝について全く言及されておりませんでした。私は、やはり被告には真摯な反省の態度がないと確信し、翌3月16日に本件提訴に踏み切りました。
本件提訴後も、被告は自らのホームページにおいて本件名誉毀損行為と同様の、自分の勝手な、思い込みに基づく誤解を、あたかも真実であるかのように主張し、それを前提として他者を一方的に批判するという形式の名誉毀損行為を繰り返しています。詳細は、原告の準備書面(2)で記載したとおりですが、このような被告の態度は、被告がいかに反省していないかを何よりもよく物語っていると思います.
(2)被告は、これらを「学問的批判の自由」「言論の自由」だなどと主張していますが、とんでもない誤りです。まず、「学問的批判の自由」というのは、事実に基づく批判でなければならないはずです。被告の本件記事は事実に基づくものではなく、私に対する誹謗中傷に他なりません。また、「学問的批判」というのであれば、その場で行うか、少なくとも反論の機会が保障された場で行うべきものではないでしょうか。しかも、本件記事で被告が批判しているのは、「発表の仕方」に関する事項で、学問的な研究の中身にかかわることではありません。発表の仕方というのは、個人によってスタイルがあることですから、それをいきなり批判する前に、発表者が何を主張するためにそのような発表スタイルを採用しているのかについて十分確認した上で批判するのが、建設的な批判のあり方ではないでしょうか。私のケースでも、直接事実を確認してもらえれば、即座に被告の誤解であることがわかったはずです。共通の事実認識に立った上での相互批判でなければ、「学問の発展」などあり得ないと思います。
「言論の自由」についても、一方的に他人の名誉を傷つける言論を行っても、それは「言論の自由」があるから許されると被告は考えているのでしょうか。
もし、そうだとしたら、それは「言論の暴力」以外の何物でもありません。
(3)私が問題だと思うのは、被告がホームページ上で一方的に事実に基づかない批判を展開していることです。個人のホームページというのは、新聞や雑誌と異なり、編集責任者などによるチェック機構が全く働きません。つまり、当該個人の倫理観だけしか歯止めにはならない訳です。これでは、被告のような自己の行為について反省もできず、他者の名誉を傷つけても平気でいる人間は、次々とホームページを利用して名誉毀損行為を繰り返すことになりかねません。
現に、準備書面(2)で記載した被告自身の記事を見ても、そのことは明らかです。つまり、私のほかにも次々と被害を受ける人が出るおそれがある訳です。
現に私の代理人をつとめていただいている弁護士の先生方や「ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議」にも、既に被害が及んでいます。
被告は、経済産業省傘下にある独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター長であり、その発言は極めて大きな影響力をもっています。したがって、自らの言論の正確性に十分注意をはらうべきです。
事実に反する言論を「言論の自由」と言って愕らない被告に対して、裁判所から法の正義を示すことによって、厳しく反省を促していただきたい。そして、研究者としての品位と節度ある言論のあり方や真の学問的批判のあり方を、ぜひ被告にわからせてほしいと願っています。
以上
〈別表〉
| 1996年3月 | シーア・コルボーンら「0ur Stolen Future」が米国で刊行される。ゴア副大統領が序文を寄せる。 |
| 1997年3月 | 環境庁(当時)、「外因性内分泌撹乱化学物質問題に関する研究班」設置 |
| 5月 | マイアミで第5回環境大臣会合開催、「内分泌撹乱化学物質は、子供への健康へのさしせまった脅威である」との認識が共有される |
| 9月 | 「(0ur Stolen Future)の邦訳『奪われし未来』刊行 |
| 1998年5月 | 環境庁、内分泌撹乱化学物質問題についての環境庁の基本的な考え方及び対応方針をとりまとめた「環境ホルモン戦略計画SPEED’98」を公表 |
| 6月 | 環境庁、「内分泌撹乱化学物質問題検討会」設置 |
| 6月 | 日本内分泌撹乱化学物質学会(環境ホルモン学会)発足 |
| 12月 | 第1回内分泌撹乱化学物質問題に関する国際シンポジウム開催(京都) |
| 1999年2月 | 「所沢産野菜の高濃度ダイオキシン汚染」のテレビ報道が行われる |
| 1999年6月 | 「ダイオキシン類対策特別措置法」が議員立法で成立 |
| 1999年12月 | 第2回内分泌撹乱化学物質問題に関する国際シンポジウム開催(神戸) |
| 2000年6月 | EU、内分泌撹乱化学物質のプライオリティリスト公表 |
| 12月 | 第3回内分泌鏡乱化学物質問題に関する国際シンポジウム開催(横浜) |
| 2001年12月 | 第4回内分泌撹乱化学物質問題に関する国際シンポジウム開催(つくば) |
| 2002年 | WHO、内分泌撹乱化学物質に関する科学的最新知見のグローバル・アセスメントの報告書を公表 |
| 2002年11月 | 第5回内分泌撹乱化学物質問題に関する国際シンポジウム開催(広島) |
| 2003年10月 | 環境省、「環境ホルモン戦略計画SPEED’98」改訂のためのワーキンググループ設置 |
| 12月 | 第6回内分泌撹乱化学物質問題に関する国際シンポジウム開催(仙台) |
| 2004年12月 | 第7回内分泌撹乱化学物質問題に関する国際シンポジウム開催(名古屋) |
| 2005年3月 | 環境省、「環境ホルモン戦略計画SPEED’98」に代わって、新たに「化学物質の内分泌かく乱作用に関する環境省の今後の対応方針についてーExTEND2005」を策定、公表 |