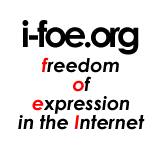準備書面(2)(2006/01/25)
準備書面(2)(被告:中西氏提出書類)
本件訴訟は2007年3月に第一審判決が言い渡され、既に確定しています。このページは、ネット上の表現を巡る紛争の記録として、そのままの形で残しているものです。
○に数字は機種依存文字であるので、半角の1)、2)などに置き換えた。
平成17年(ワ)第914号損害賠償請求事件
原告 松井三郎
被告 中西準子
準備書面2
2006(平成18)年1月25日
横浜地方裁判所民事第9部合議係 御中
被告訴訟代理人 弘中惇一郎
同 弁護士 弘中絵里
記
1 本件本訴事件の審理対象
訴状で明らかなとおり、本件で名誉毀損の有無が問題になっているのは、甲第1号証のホームページ記事の6ページの2行目から8行目と16行目から23行目の部分であり、それ以外の部分ではない。
2 原告の主張の撤回要求
ところで、原告は原告の準備書面2の6項以下(12ページ以下)で、本件名誉毀損とは関係のない別個の記事を取り上げて、いろいろと被告の悪口を言っている。
しかしながら、一般に、別の機会に別の記事で名誉毀損行為があったことを指摘することにより、問題の記事の名誉毀損が立証できるなどということはあり得ないし、そんな方法による立証が許されるはずもない。「週刊新潮」や「週刊文春」は、名誉毀損事件でたびたび被告とされているが、別の記事の存在により問題の名誉毀損記事の立論立証が認められたことなど聞いたこともない。
例え準備書面の形をとったとしても攻撃防御方法として許容される域を超えて不当に被告の名誉毀損を行うことを続けるのであれば、被告としては別個に法的責任を追及することも考えるが、とりあえず、無意味かつ不当な悪口をやめていただきたい。したがって、この準備書面(2)の5項以下における主張をすべて撤回することを求めるものである。
3 本件記事の問題 ナノ粒子について
(1)そして、原告の準備書面2から、以上の無意味かつ不当な主張を削除すると、準備書面は3分の1程度のスリムな姿になるので、これに対して必要な反論を行う。
(2)まず、原告は、一般読者の普通の読み方での本件記事の事実摘示が
A 「原告が、すでに環境ホルモンは終わったものと考え、別の新たな課題(ナノ粒子の有害性)へと関心を移している」
B 「ナノ粒子の有害性を問題にするにあたって、原告が、原論文を読まずに、あるいは十分に吟味せずに、新聞記事をそのまま紹介した」
であるとし、それを前提に主張している。
(3)ところで、本件記事の主要な部分が、ナノ粒子の有害性についての問題提起の仕方に対する批判であることは、一読して明らかである。すなわち、問題の記事は「最初の情報発信に気をつけよう」と題して論じられている上、内容としても、ナノ粒子の問題についての記事がほとんど全部を占めているのであり、環境ホルモンについては「環境ホルモンは終わったという意味である」の11文字しかない。この11文字だけでは、事実摘示の内容は不明確であり、名誉を毀損するような事実摘示とは言えない。
(4)名誉毀損の成立の有無は、記事の主要部分によって判断されるのであり、枝葉末節部分で判断されるものではない。このことは判例学説上確立している。
本件記事中の「環境ホルモンは終わった」の部分が、主要部分とは言えないことは自明である。
従って、本件で、名誉毀損として問題になるのは、このナノ粒子の有害性についての問題提起についての事実摘示が真実であるか否か、また、それに対するコメントが人身攻撃的なものでないか、ということに尽きるはずである。
(5)本件記事におけるナノ粒子についての事実摘示が1)原告が新聞記事のスライドを見せて「次はナノです」として、ナノ粒子の有害性を問題提起しながら 2)新聞記事の紹介以上に自分の考えや原論文を読んでの意見などを付加したものではなかった ということに尽きることは甲1号証で明らかである。その余は、それを前提とする被告の見解の披瀝であることも甲1号証で明らかである。
(6)なお、原告は、前述の通り、「原告が、原論文を読まずに、あるいは十分に吟味せずに」との事実摘示をしたというが、そのような事実摘示のないことは甲1号証で明らかである。「自分で読んで伝えてほしい。でなければ、専門家でない」の部分は一般論であるが、仮に、原告のことについても指摘しているとしても、ここで被告が問題にしているのは「自分で読んで伝える」ことであり、「読むこと自体」ではなく、まして「十分に吟味すること」などではない。
念のために述べるが、「読む」ことと「読んで伝える」こととはまったく意味が異なる。読んで勉強していても伝えることをしないことはいくらでもあろう。本件発表は、「リスクコミュニケーション」を基本テーマとして行われた場でのものである。「リスクコミュニケーション」においては、いかに「伝えるか」が中心テーマとなっているのであり、陰で「勉強」しているかとか、陰で「吟味している」とかが問題となるものではない。
そもそも、リスクコミュニケーションの領域でなくても、学者は、発表した内容それ自体により評価されるのであり、発表したものそのものに対して批判を受ける立場にある。学者としての相互批判も、現に発表したものについて行われるのである。
(7)ナノ粒子というきわめて重大な問題について、乙5号証ならびに甲8号証第13図の新聞記事スライドだけを根拠に、環境汚染の可能性というような重大な発表を、しかも、リスクコミュニケーションのありようが問題となっている場で行っておきながら、陰で勉強していたのにそれを認めてくれないとして怒るようでは、およそ学者としての基本的心構えができていないというべきである。
このナノ粒子についての発表の仕方が、唐突でお粗末であったことは、乙5号証の録音内容及びスライドとして示したのが新聞記事(甲8号証第13図)だけであったことからして明瞭である。原告は、新聞記事の評価について問題にしている(準備書面2の29ページ)が、仮に、原告が、本気で、新聞記事のみを提示するような発表が許されると考えているのであれば、論外である。
4 環境ホルモンについて
(1)なお、原告が「事実摘示」と主張するA 「原告が、すでに環境ホルモンは終わったものと考え、別の新たな課題(ナノ粒子への有害性)へと関心を移している」の点についても、念のため、反論を加えておく。
前述の通り、この部分は本件記事の主要部分とは言えず、本来問題にする必要はないのであるが、それを措くとしても、以下のとおり原告の主張は失当である。
そもそも、被告が本件記事で述べたのは、被告として、原告の発言の趣旨を「社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなくナノ粒子である」というものと受け止めたということである。問題とされている箇所の結びは「・・・という意味である」となっているが、これは被告の解釈を示すものであることは明瞭である。
被告は、原告の「考え」や「関心の移行」などという原告の内心の問題には興味もないし、そのようなことを論じる意志もなかった。
一般論としても、これからの社会的主要なテーマがナノ粒子になっても、個人としては従来の環境ホルモンの研究をこつこつと持続することはいくらでもあろう。被告は、原告の個人的な研究の関心がどこにあるのかは知るよしもないし、関心もない。しかし、「(今後)社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子である」かどうかは、研究者に共通する重要なことであり、被告としても見逃せない発言である。そのような重大な問題提起を前述したようなお粗末な形で行われたので、これを批判したものである。
以上のとおりであるから、被告は、原告自身の環境ホルモンへのこだわりや関心の程度について事実摘示したことはなく、原告の主張は前提を欠くものであり、失当である。
(2)なお、乙5号証に明らかなとおり、原告は、発表の締めくくりとしてナノ粒子の問題を提起し、その中で、「今回学んだ環境ホルモンの研究はどうやって生かせるのか。私は次のチャレンジはナノ粒子だと思っています」と発言したのである。
一般に、「あることで学んだことを次のテーマでどう生かすのか」という言い方をするのは、あることについては一段落したということを前提とする。一通りの検討が尽くされたのでなければ、「学んだこと」の整理も認識もできるはずがないからである。
また、「次のチャレンジ」という言い方をするときは、取り組むべき対象が移行したことを意味する。
したがって、発表の締めくくりとして、原告がこのような発言をすれば、それを聞く立場としては、発言の趣旨を「(今後)社会が関心を持つべきテーマは、もはや環境ホルモンではなく、ナノ粒子である」と受け止めるのは当然のことである。
5 原告への質問を経なかったこと等
(1)なお、原告は、原告の発言の趣旨について、シンポジウムの会場で質問すべきだったという主張をしている(準備書面2の9ページ、10ページ)。
シンポジウムの場というのは時間的制約があり、原告の主張は現実的ではないが、それを措くとしても、本件で、本件の記事発表の前提として、原告に対する質問の必要など考えられないことである。すなわち、原告のナノ粒子についての問題提起の仕方があまりにお粗末であることは歴然としていることであり、質問の余地がない問題である。なお、原告の内面的な関心の移行については、被告として興味もなく問題にする気もなかったことである。本件記事でもそのようなことを摘示してはいないことはすでに述べた。
(2)また、原告は、本件記事をホームページという反論できない一方的な媒体で行ったことが問題としている。原告は、具体的には、本件のような批判は直接コミュニケーションの保障された場でのみ行うべきであったとする(原告準備書面の10ページ、18ページ、反訴答弁書4ページ等)。
しかし、一般的にも、他の学者の発表内容や方法論についての批判は、論文その他の一方的な発言の媒体で行うものであり、直接コミュニケーションの保障された限局された場で行うべきなどという議論は聞いたこともない。
反論、再反論あるいは相互批判などは、それ自体は一方的な発信手段である論文やホームページ、インターネットなどで行われるのが一般であり、現に、原告自身もインターネットにより、被告に対する批判ないし反論を行っている。
原告の主張は、現実離れしたものとしか言い様がない。
6 肩書きの誤り
原告は、 被告が原告の肩書きの一部を誤ったことを問題にして、意図的に行ったとか、これが人格攻撃の裏付けだなどと主張している(原告の準備書面2の11ページ)。
この種の肩書きを正確に覚えるのが容易なことでないのは公知の事実と思うが、この程度の誤りから、上述のような主張を導き出すのは、論理の飛躍も甚だしいこと明らかである。このような主張態度は、まさに本件訴訟が人格攻撃を目的にしたことを裏付けているものである。
7 事実摘示の真実性に関連して
原告は、準備書面(2) の8ページで、「有害性=死というようなリスクの捉え方では把握できないものがあり」「その点が原告と被告・・との相違点」と主張している。しかし、被告は、「有害性=死のみ」などという捉え方をしていないし、このことは被告の著書を読めば容易に認識できることである。
本論との関係は薄いので詳しい主張は避けるが、この点の原告の主張が誤りであることを指摘しておく。
以上